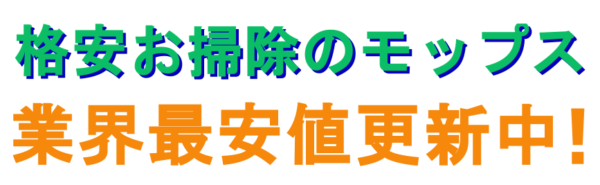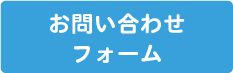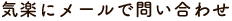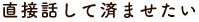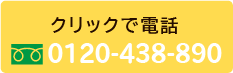コロナに負けない!免疫力アップのための栄養対策と健康法3つ【2021年版】

コロナ渦である今、パンデミックの感染対策として「免疫力アップしたい」と考える機会が増えているのではないでしょうか?
免疫力アップを叶えるために必要なのは、「栄養対策」と「健康法」という2種類の対策方法です。
この記事で解説する栄養対策と健康法を日々実践していけば、新型コロナウイルスに限らず、あらゆる病原性のウイルスに対抗できる体質に変わっていけます。
さらには、日々の健康管理の質を上げていくこともできるので、身近な風邪や病気にかかりにくい健康体で日々を過ごせる確率がアップするのです。
ではさっそく、免疫力アップを目指すために日頃からできる栄養対策と健康法3つについて解説していきます。記事の最後には、それぞれの方法を実践するときのポイントもまとめていますので、着実に免疫力アップを目指すためにぜひ参考にしてください。
免疫力アップを目指すために日頃からできる栄養対策3つ

はじめに、免疫力アップを目指すために日頃からできる栄養対策をご紹介していきます。
日々の食事やサプリメント補給等によって「バランスよく」栄養を摂取することは大前提となりますが、ここで取り上げる栄養素は「タンパク質」「ビタミンD」「セレン」の3つです。
「タンパク質」「ビタミンD」「セレン」の3つの栄養素は、2020年以降に発表された研究報告の中で、新型コロナウイルス感染症との間で明確な相関関係がみられているものになります。
以下の項目別に、3つの栄養素について解説していきますので参考になさってください。
・その栄養素がもつ効果
・1日あたりの摂取目安量
・その栄養素を多く含む食品
・その栄養素の効率的な摂取方法
栄養素の解説で得た知識を活かして各栄養素をバランスよく摂取することで、免疫力アップとしての栄養対策ができますので、ぜひこのまま記事を読み進めていきましょう!
栄養対策その1.タンパク質を摂取する

免疫力アップを目指す栄養対策として、タンパク質の摂取は欠かせません。
タンパク質は免疫細胞の土台作りをする重要な栄養素です。
タンパク質またはタンパク質を構成する栄養素であるアミノ酸不足がみられると、免疫機能が損なわれ、感染症にかかりやすくなってしまいます。また、ウイルスやがん細胞等を攻撃してくれる「T細胞」というリンパ球(白血球)が減ることで、免疫力の低下を招いてしまうのです。
逆に、理想的なタンパク質の量を摂取しておくことで、
・免疫細胞が活性化する
・T細胞を含めて白血球の数が増える
・質の良い抗体ができる
といったメリットが得られるわけです。
だからこそ、免疫力アップを目指すためには日々タンパク質の摂取が必要になります。
《タンパク質の「1日あたりの理想的な摂取量」は?》
1日あたりの理想的なタンパク質の摂取量には諸説あるため明確な定義はありません。ただ、欠乏症を回避するためのタンパク質維持必要量として、「1g/kg 体重/日」とされています。つまり、体重が60kgの人とすると、1日に60gほどのタンパク質を摂取するのがおすすめとされているわけです。
(出典元:日本人の食事摂取基準(2020年版)|厚生労働省)
《タンパク質を多く含む食品は?》
免疫力アップを目指すための良質なタンパク質を多く含む食品は「肉類」「豆類」「卵類」です。
ここでは、文部科学省の『食品成分データベース』を利用し、「肉類」「豆類」「卵類」にあたる食品100gあたりのタンパク質含有量をまとめていきます。
| 食品 | タンパク質の含有量(食品100gあたり) |
| 鶏肉ささみ(ゆで) | 29.6g |
| きな粉(脱皮大豆・黄大豆) | 37.5g |
| 鶏卵(ゆで) | 12.9g |
肉類の中では、ゆでた鶏ささみ肉が最も効率よく良質なタンパク質を摂取できる食品です。ほかに、牛肉、豚肉、くじら肉など「赤みのお肉」にも、100gあたり20g前後のタンパク質が含まれています。
豆類の中では、脱皮大豆・黄大豆を使用して作られたきな粉が圧倒的に多くのタンパク質を含んでいます。同じく黄大豆を使用した全粒大豆のきな粉でも、100gあたり36.7gのタンパク質を摂取することができます。
その他、納豆、油揚げ、生湯葉にも100gあたり20g前後のタンパク質が含まれているので、積極的に摂取したいところです。
卵類の中では、ゆでた鶏卵に良質なタンパク質が多く含まれています。ただし、うずらの卵や他種の卵の水煮缶でも100gあたり10g前後のタンパク質を摂取することができます。
《タンパク質の効率的な摂取方法は?》
タンパク質は、タンパク質の合成をするはたらきをもつマグネシウムとセットで摂取すると、その効果を効率的に発揮できます。タンパク質を多く含む肉類のうち「ゆでた鶏肉ささみ」は、100gあたり34mgのマグネシウムを含んでいます。
卵類であれば、「ゆでた鶏卵」が100gあたり11mgのマグネシウムを含みます。また、豆類であれば「生湯葉」が100gあたり80mgとたくさんのマグネシウムを含んでいます。
そのため、手軽に免疫力アップをしたいというあなたは、毎日の献立に「蒸し鶏ごはん」「ゆで卵」「鶏ささみのスープ」「味付け生湯葉」等、楽しく調味しながら加えてみることをおすすめします。
栄養対策その2.ビタミンDを摂取する

ビタミンDは免疫力アップを目指すほか、新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぐ可能性があるとされる重要な栄養素です。こちらも免疫力アップとしての栄養対策に必須の栄養素と言えます。
新型コロナウイルス感染症患者212例をもとに研究を進めたサウスイースタンフィリピン大学は、新型コロナウイルス感染症の重症度が増すほどビタミンDの血中濃度が低いという研究結果を発表しました。
つまり、ビタミンDが欠乏した状態で新型コロナウイルス感染症にかかった場合、症状が重症化しやすい、あるいは回復しにくいという捉え方ができるわけです。
こちらの研究報告は2020年4月15日にプレプリントとして改訂・発表され、まだ参考文献として正式に認められたものではありません。ですが、ピタミンDには、
・抗炎症作用
・ウイルスを殺すための抗微生物ペプチドの生成
といった免疫力アップに関連するはたらきがあります。サウスイースタンフィリピン大学の研究報告のみならず、こうした免疫力アップに関連したはたらきからみても、ビタミンDは欠乏しない程度に摂取しておきたい栄養素であることがわかります。
また、ビタミンDのもつ抗炎症作用には、新型コロナウイルス感染症の一般的な症状である「肺炎」を食い止めるはたらきがあるとされています。ビタミンD欠乏の傾向にあるわたしたち日本人が、感染後の肺炎から早期に回復するためにも、栄養対策の一環としてビタミンDの摂取をしておくべきでしょう。
《ビタミンDの「1日あたりの理想的な摂取量」は?》
厚生労働省の『日本人の食事摂取基準(2020年版)』によれば、18歳~64歳までは1日あたり8.5㎍のビタミンDを摂取することが理想的だとされています。また、65歳以上の高齢者においても、現状は同じビタミンD量の摂取が望ましいと言われています。
ただし、1日あたり8.5㎍のビタミンDを摂取するだけでなく、適度な日光浴もあわせて行うことが推奨されています。1日に必要なビタミンDを食事だけで摂取することは現実的でないため、不足分を補うために太陽光(紫外線)を浴びることがおすすめされているのです。
ビタミンDと太陽光(紫外線)にどのような関係があるかについては、次章で取り上げる健康法の中で解説しますので、ここでは言及しません。
(出典元:日本人の食事摂取基準(2020年版)|厚生労働省)
《ビタミンDを多く含む食品は?》
免疫力アップを目指すためのビタミンDを多く含む食品は、「魚介類」「きのこ類」「乳類」「卵類」です。ここでは、公益財団法人長寿科学振興財団の運営する『健康長寿ネット』を利用し、「魚介類」「きのこ類」「乳類」「卵類」にあたる食品100gあたりのビタミンD含有量をまとめていきます。
| 食品 | ビタミンDの含有量(食品100gあたり) |
| あん肝 | 110㎍ |
| きくらげ(乾燥) | 85.4㎍ |
| 牛乳 | 0.3㎍ |
| 鶏卵・卵黄(生) | 5.9㎍ |
魚介類の中では、あん肝がビタミンDを多く含みます。ただし、スーパー等であん肝を入手するのは結構難しいでしょう。そんな時は、半乾燥タイプの釜揚げしらすなどで代用するのがおすすめです。
しらすにも100gあたり61㎍のビタミンDが含まれています。また、生の紅鮭(お刺身等)は100gあたり33㎍、生のまいわし(お刺身等)は100gあたり32㎍のビタミンDが含まれているため、週替わりで色々なお魚を食べるとよいでしょう。
きのこ類の中では、乾燥きくらげが圧倒的に多くのビタミンDを含んでいます。その他、乾燥しいたけにも100gあたり12.7㎍のビタミンDが含まれているので、炒め物や煮物等に入れてきくらげとあわせて摂取することをおすすめします。
乳類の中では、牛乳がピタミンDを含んでいます。100gはコップ1杯程度に相当するので、1日の中でコップ1杯の牛乳を飲むと0.3㎍のビタミンDを摂取できることになるわけです。
また、卵類の中では、生の鶏卵の卵黄部分にビタミンDが含まれています。朝食を「卵かけごはん」にする等の工夫をしつつ、他の食品とあわせて摂取すると免疫力アップとしての栄養対策になります。
《ビタミンDの効率的な摂取方法は?》
タンパク質と同様、ビタミンDもマグネシウムとセットで摂取することで、その効果を効率的に発揮できます。ビタミンD・マグネシウムはどちらも筋肉や骨の代謝と関わる栄養素です。
また、マグネシウム単体でみても、体内に取り込まれた栄養素の消化・代謝という役割があるため、摂取したビタミンDの吸収効率を上げるためにもセットで摂取しておきたいものです。
マグネシウムを含む食品については、『タンパク質の摂取』で解説したとおり、「ゆでた鶏肉ささみ」「ゆでた鶏卵」「生湯葉」等が挙げられます。ビタミンDを含む食品とセットで、毎日の献立に盛り込むようにしましょう。
栄養対策その3.セレンを摂取する

抗酸化作用や免疫活性の効果を持つミネラルとして知られるセレンも免疫力アップを目指し、ウイルス感染しないために摂取すべき栄養素のひとつと言えます。
私たちは、常日頃から酸化ストレスを受けています。ここで言う酸化ストレスとは、呼吸、紫外線、大気汚染、喫煙、精神的なストレスなどを主な要因として受けるストレスの一種のことです。新型コロナウイルスなどの感染症やがんになることでも酸化ストレスは発生します。
セレンは、こうした酸化ストレスから私たちを守るために必要なミネラル・栄養素なのです。
実際のところ、セレンの摂取量が最も多い地域とされる中国・湖北省の恩施市では、新型コロナウイルス感染症の患者の回復率が、湖北省全都市の平均より3倍も高いという研究結果がでています。
逆に、セレンの摂取量が最も少ない地域とされる中国・黒竜江省では、新型コロナウイルス感染症による死亡率が、湖北省全都市の平均より4倍も高いという研究結果になったのです。
こうした結果から、今後コロナウイルス感染症にかかる可能性を考慮した場合、セレンを摂取しておいた方が安心できると考えることができます。
(中国における地域のセレン状態とCOVID-19症例の報告された結果との関連|The American Journal of CLINICAL NUTRITION)
《セレンの「1日あたりの理想的な摂取量」は?》
1日あたりのセレンの理想的な摂取量にも諸説ありますが、健康長寿社会の発展を目的として運営される公益財団法人長寿科学振興財団によればその推奨量は「18歳以上の男性で30㎍・女性で25㎍」とされています。
なお、上限量は18~29歳の男性で420㎍・女性で330㎍とされています。上限量が最も多いのは30~49歳までの男性で460㎍とされています。これは、老化とともに体内の抗酸化作用が弱まることから想定される値ですが、過剰摂取はセレンの毒性を強めることにつながるため避けましょう。
《セレンを多く含む食品は?》
免疫力アップを目指すためのセレンを多く含む食品は「魚介類」「肉類」「海藻類」「卵黄」です。ここでも、文部科学省の『食品成分データベース』を利用し、「魚介類」「肉類」「海藻類」「卵黄」にあたる食品100gあたりのセレン含有量をまとめていきます。
| 食品 | セレンの含有量(食品100gあたり) |
| あん肝 | 200㎍ |
| 豚レバー | 67㎍ |
| あおのり | 7㎍ |
| 鶏卵、全卵 | 32㎍ |
魚介類の中では、ビタミンDと同様、あん肝がセレンを多く含む食品です。ただ日々の献立であん肝を用意するのはやはり大変でしょう。手軽に食べられる食品としては「かつお節」がおすすめです。
かつお節は100gあたり320㎍ものセレンを含みます。1パックあたり1.5gほどの分量として換算すると、セレンの含有量は4.8㎍なので、他の食品と合わせつつ推奨量を摂取するのが良いでしょう。
肉類の中では、豚レバーに比較的多くのセレンが含まれています。レバーが苦手な方は、脂身のない豚もも肉でも100gあたり23㎍のセレンを摂取することができます。あるいは、若鳥のささみ肉にも100gあたり22㎍のセレンが含まれているので、好みに合わせて摂取しましょう。
海藻類の中では、あおのりが比較的多くのセレンを含んでいます。乾燥ひじきで代用しても100gあたり7㎍と同じ量のセレンを摂取できます。また、卵黄の中では、鶏卵・全卵にセレンが多く含まれているので、ご紹介した他の食品とうまく組み合わせて調味したうえで食べることをおすすめします。
《セレンの効率的な摂取方法は?》
セレンはビタミンEと組み合わせて摂取することで、その効果を最大限に発揮できます。そのため、ビタミンEを含む玄米・大麦を精白米の代わりに食べるだけでも、効率的なセレンの摂取が可能です。
精白米にはほとんどセレンが含まれていないため、いち早く免疫力アップを目指すのであれば、お米から変えてみるという方法をおすすめします。
「お米すべてを玄米や大麦に変えるのはちょっと…」という方は、1対1の割合で白米と玄米をブレンドし、魚介類や卵黄など他の食品(おかず)でセレンの推奨量を満たすようにしてみましょう。
免疫力アップを目指すために日頃からできる健康法3つ

続いて、免疫力アップを目指すために日頃からできる健康法をご紹介していきます。
月並みのように思う方もいるかもしれませんが、ここからご紹介していく健康法は「運動」「ダイエット」「日光浴」の3つです。
本章でもまた、2020年以降に発表された研究報告をもとに3つの健康法がいかに大切なのかを解説していきます。また、各健康法別に、
・その健康法の効果
・その健康法のやり方
上記の項目も交えつつお伝えしていきますので、免疫力アップを目指して長い目でみながら取り組んでみてください。では、このまま記事を読み進めていきましょう。
健康法その1.運動

適度な運動は免疫力アップのために必要な健康法です。運動により心拍数を上げることで、ウイルス・がん細胞等を撃退してくれるリンパ球の数が増えます。つまり、新型コロナウイルスのような病原性のウイルスを体外に追い出そうとするはたらきが強まるわけです。
また、運動には心身の健康を保つ効果もあります。パンデミック下で外出自粛を言い渡され、ストレスフルに過ごしている人は多いことでしょう。
そんな時に運動することで、心身をリラックスさせるための副交感神経が優位にはたらくようになるため、脳内から「セロトニン」という幸福ホルモンが分泌され、ストレスが和らぐのです。
《運動のやり方は?何をどのくらいの時間やればいいの?》
大前提として、運動をする際は「自宅または自宅付近」で行いましょう。一念発起してジムに通うなどする必要はありません。特に日頃から運動する習慣のない方は、運動へのハードルや面倒という気持ちを下げることから始めることをおすすめします。
また、忘れてはいけないのが「1日の運動時間を短く済ますこと」です。一般に推奨されている運動量は週に150分(1日あたり30分)ですが、現役外科医である石黒医師によれば、必要な運動量は1日10分でも十分とのこと。あるいは、
・1日5分の筋トレ(腕立て伏せ、腹筋等)
・1日4分~10分のHIIT運動・高強度インターバル運動(スクワット等)
上記のような1日10分以下の「自分の体重を使った筋トレ」でも適度な負荷がかかり、運動効果を得られるとされています。まずは、あなたが負担に感じない程度の時間で運動をすることが、免疫力アップに繋がる健康法となるわけです。
健康法その2.ダイエット

免疫力を下げないための健康法として、ダイエットも推奨されています。いわゆる肥満体型になると、蓄積された脂肪組織(内臓脂肪)に炎症が起こり、免疫機能にダメージが生じやすくなります。
つまり、免疫力が低下してしまうために、新型コロナウイルス感染症等の感染症にかかりやすくなるのです。さらに言えば、新型コロナウイルス感染症等にかかった場合、免疫機能にダメージが生じている分だけ重症化・死亡しやすいとも考えられます。
その他、睡眠時無呼吸症候群等を誘発する原因にもなります。よって、太ってきたと感じたらすぐに減量・ダイエットに取り組むことが、免疫力を下げないための健康法になるわけです。
《ダイエットのやり方は?》
ダイエットを効率よく成功させるためには、カロリー消費のしづらい夜遅くの時間帯を中心に「食欲をコントロールすること」が何より大切です。食欲とは、食欲ホルモン「グレリン」を指します。グレリンは胃袋、小腸、すい臓、脳の一部から分泌され、わたしたちの食欲を刺激します。
実のところ、グレリンは、わたしたちが普段食事をする時間帯に影響を受けて活動を始めるのです。つまり、いつも食事をする時に応じて食欲が湧くようなしくみになっているということになります。
しかもこのときに湧く食欲は「空腹なとき」と「空腹でないとき」の両方のタイミングで作用するのです。このような事実からどのように食欲をコントロールすればよいのか。そのやり方は以下2つです。
・おなかに溜まりやすい食物繊維を摂取する
・食事後~次の食事の時間帯までの間、「こまめに」水分補給をする
※つまり、ぐびぐびと一気に量を飲まない事が大事です。
※そして、食事中と食事直後は、なるべく余計な水分をとらないようにしてください。水分をとりすぎることで井の中の食物が消化されにくくなり、腸内でもよくない影響が出やすくなるためです。腸内が乱れれば確実に免疫がおちますので、非常に重要な習慣となります。
この2つの方法を実践することで「何か食べたい」という状態をすぐに作らなくて済みます。要するに、空腹時にも食欲を湧かせるグレリンのはたらきを抑えることができるのです。
すると、食欲に負けがちだった夜遅くの時間帯にも食事を控えられたり、ファスティング等にも成功しやすくなったります。結果的に減量がしやすくなり、肥満体型を早期に卒業できる可能性が高まるため、ぜひ2つのやり方で食欲をコントロールできるようになりたいものです。
《食欲を抑えるダイエット効果のある食品・飲料》
ダイエットの効率をより高めるために、ここでは食欲をおさえる効果のある食品・飲料をご紹介していきます。食欲のコントロールに挑戦する際には、ぜひ以下の食品・飲料を取り入れてみてください。
・グルコマンナン(こんにゃくマンナン)

海洋性の食物繊維のうち最もダイエット効果が高いと言われており、こんにゃくやチアシードに含まれるダイエット成分としても知られています。摂取すると胃の中にある水分を吸収して膨らみ、満腹感を得られます。
グルコマンナンはサプリメントとして市販されている場合がほとんどですので、食事を控えたい時間帯等にあわせて適量飲んでおくと、食欲のコントロールができます。
・緑茶

脂肪を減らす効果のあるカテキン(EGCG、エピガロカテキンガレート)や、食欲の抑制・脂肪燃焼効果のあるカフェインを有効成分とする緑茶もダイエット飲料としての効果が高いと言えます。
カフェインと言えばコーヒーを思い浮かべる方もいるでしょう。たしかにコーヒーにも、1杯あたり100mgのカフェインが含まれています。1日1~2杯を目安に飲むことで食欲をコントロールしつつ、脂肪を燃やすことができるでしょう。
ただし、このようなコーヒーの作用は男性にはたらきやすく、女性にははたらきにくいと言われています。そのため、性別を問わずダイエット効果を期待できる飲料としては、緑茶の方が優れているのです。
健康法その3.日光浴

免疫力アップを目指すには、日々の日光浴も欠かせません。皮膚に紫外線を浴びることで免疫力アップに欠かせないビタミンDを生成することができます。
紫外線には「UV-A」と「UV-B」の2種類あります。ここで言う紫外線とは、一般にUV-Bという種類を指します。UV-Bは紫外線のうち95%を占め、皮膚の表面まで到達できるタイプです。
一方、UV-Aの方は紫外線のうち5%のみを占め、「ビタミンDを生成できるほど強い紫外線ではない」とされてきました。しかし最近の研究で、UV-Aでも別の角度から免疫力を高めて感染症対策が有意にできるということがわかっています。以下に、例の研究内容を端的にまとめています。
・外部の木々、鉄柱などのモノにUV-Aが当たることで、そこに付着していたウイルスが不活化する
・UV-Aを浴びた人間の皮膚には、血管拡張作用のある一酸化窒素が生成される
研究内容の後者で取り上げた「一酸化窒素」には、血圧を下げてくれる効果があります。新型コロナウイルス感染症にかかりやすい人の特徴として高血圧が挙げられているため、高血圧の方にとって、UV-Aを浴びることは立派な対策となるわけです。
このように、UV-A・UV-Bのいずれも、免疫力アップに役立つ紫外線なのです。紫外線の種類を問わず、ひとつの健康法として日光浴も取り入れましょう。
(参考:紫外線A放射線とCOVID-19による死亡:多国間研究|medRxiv)
《日光浴のやり方は?どのくらいの時間浴びればいいの?》
日光浴をする際は、肌の10%程度を露出させる「半袖・半ズボン」の服装が適しています。つまり、両腕・両足を日光に当てることで適量の紫外線を吸収し、ビタミンDを生成することができるわけです。
1日に摂取すべきビタミンDの量を紫外線量に換算できる単位で表すと「2,000~5,000IU」となります。実際に、「東京都内」「夏時期」「午前中」「半袖・半ズボン」という条件下で30分ほど日光浴を行った場合、800IU(推奨量の3分の1強)のビタミンDが生成するとされています。
秋や冬に差しかかると日光浴で浴びられる紫外線量は減少するので、それに比例して日光浴から生成されるビタミンDの量も減ります。そのため、上記の例と同じく1日30分間の日光浴をしたとしても、1日に摂取すべきビタミンDの量には満たないのです。
日光浴の目安時間は1日30分と考えてもOKですが、秋冬など紫外線によるビタミンDの生成量が落ち込みやすい季節には、「日光浴+食事/サプリメント」を心がけ、ビタミンDを摂取しましょう。
また、「窓越しの日光浴」は効果がないのでご注意ください。窓は紫外線を遮断してしまうため、ベランダに出る・家の外に出る等したうえで紫外線を浴びることを意識しましょう。「日焼け止め」も紫外線をブロックしてしまうため、日光浴の前は塗らないようにする必要があります。
栄養対策と健康法を実践するときのポイント

ここまで免疫力アップを目指すために日頃からできる栄養対策と健康法を解説してきましたが、最後に「栄養対策と健康法を実践するうえでのポイント」をまとめていきます。
何でも過剰はNG
栄養対策にせよ健康法にせよ、何でも過剰に取り組むのはNGです。例えば、推奨量を守らずにご紹介した栄養素を摂取すれば、『過剰症』として吐き気等の副作用を引き起こす恐れがあります。
あるいは、運動習慣のない方が急に1日5kmのランニングに挑戦すれば、過剰な運動による免疫力低下を招くこともあるのです。栄養対策と健康法のどちらも「正しいやり方」に沿うことで、本来の目的である免疫力アップを目指せるということを理解しましょう。
毎日の継続・習慣化が肝心
栄養対策・健康法のどちらも毎日の継続・習慣化が肝心です。例えば、運動習慣のない方が「今日はやってやるぞ!」という意気込み任せに多量の運動をしても、翌日以降は続かないでしょう。
こうした1日限りの気分、または三日坊主のチャレンジに終わるのではなく、日々無理なくコンスタントに継続・習慣化していくことを目指しましょう。特に今回の新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックは長く続くことが予想されています。
・栄養対策としての献立を考え続けてストレスフルになるなら「サプリで代用」も視野に入れる
・その場限りの気合いで運動するのではなく、毎日続けられる運動目標を設定する
このように、栄養対策・健康法のどちらも毎日続ける・習慣化するという意識のもとで取り組み、蔓延するウイルス等と共生できるような免疫力をつけていくことが大切です。
組み合わせて効果アップ
栄養対策と健康法それぞれを章立てて解説してきましたが、どちらも組み合わせることで免疫力アップの効果が最大限に発揮されます。どちらか一方だけを実践するのでは効果が半減してしまうので、この点についても注意が必要です。
例えば、栄養対策として各種栄養素を摂取しても、肥満体型のままダイエットをせずにいれば、免疫力は思うように上がりません。なぜなら、先にお伝えしたとおり、肥満であるほど免疫機能にダメージが生じやすいためです。
栄養対策をしつつダイエットにも取り組むというように、栄養対策と健康法を組み合わせてこそ、免疫力アップの効果が高まるということを忘れないでおきましょう。
まとめ
免疫力アップを目指すために日頃からできる栄養対策は、「タンパク質」「ビタミンD」「セレン」を適量摂取するというものです。この他にも必須栄養素となるビタミン・ミネラルをバランスよく摂取しましょう。
また、この記事でご紹介した、「栄養対策として摂るべき栄養素に相乗効果をもたらすマグネシウムやビタミンE」の摂取もしておきたいものです。
他方、免疫力アップを目指すために日頃からできる健康法は、「運動」「ダイエット」「日光浴」を行うというものです。いずれも基礎的な健康法ではあるものの、ついつい面倒に思ってやらずじまいになりやすい方法ですので、パンデミック下にあるというこの状況を機に少しずつ取り組んでみてください。
栄養対策と健康法を組み合わせて実践する習慣ができれば、「コロナと共生していく時代」に対応できるだけの免疫力がついてきます。
最後に、この記事でご紹介した栄養対策と健康法は、あなた自身が今確実にできることと言えます。感染症や病気を患うことを恐れるばかりでなく、まずは「1つずつでもやってみよう」という意識をもって取り組んでみてください。
業界最安価格で、定期的にお部屋を清潔に保ちたい方は、
忙しい中コロナ対策をしたいけど、なるべく安く!というかたは、こちらから、お気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】業界初!モップスの「永久割引制度(リピ割)」とは?
これは、モップスで2回目以降のサービスご利用時に使える制度なのですが、
例えば、あなたが、初めてモップスのサービスをご利用になったとき、作業終了後、モップスから「リピ割チケット」をプレゼントいたします。
で、このチケット1枚で「10,000円以上の単品メニュー」がすべて2000円引きになるうえに、チケット一枚で同時に複数のメニューを申し込むことも可能になる制度となります。
「今だけ!」永久割引権利プレゼント
さらに、この制度は、サービスを利用するたびに「永久に」適用されます。
つまり、今なら、どのようなコースでも、一度でもモップスのサービスを申し込んでくれたお客様にはチケットをお渡ししますので、2回目以降、そのチケットを出していただければ、その都度、各メニュー(10,000円以上の単品)について2,000円引きでサービスを受けられるということです。
言い換えると、一度でもモップスのサービスをご利用になれば、モップスとあなたが存在する限り、半永久的に使える「2000円引きパスポート」を手に入れることができる、ということ。
永久割引権利が得られるのは、本当に「今だけ」
この制度は大評判なので、なるべく続けたいと思っているのですが、定期的にリピートしてくださるお客様が一定数以上になった場合、スタッフの人数によっていやでも制限が生じる為、仕事の質を保つためには必ず一旦停止しなければなりません。
ですから、煽りでも、演出でもなく、本当に、この制度が停止する前に、権利をゲットしていただけたお客様だけが、めちゃくちゃお得になる状態なのです。
ちなみに、お掃除機能なしのエアコンクリーニングを、初回8,000円で利用するだけでも、この永久権利がもらえますので、「お試し」でトライするコストも業界最安と言えるでしょう。
モップスのコンセプトは「お客様を徹底的にえこひいきする!」ですので、リピーターのお客様には、他社圧倒の超お得な制度で歓迎いたします!
是非ご利用ください。
リピ割チケット(永遠に2000円引き)が適用できるコース一覧
- お掃除機能付きエアコンクリーニング
- 通常エアコンクリーニング
- トイレクリーニング
- 浴室クリーニング
- キッチンクリーニング
- レンジフードクリーニング
モップス2回目(チケットご提示)ご利用イメージ
例えば、モップス2回目でチケットをお持ちの方が通常エアコン1台とキッチン、レンジフードのクリーニングをお依頼くださった場合
●通常エアコン12,000円が
→10,000円に!
(リピート価格2,000円引き)
●キッチン16000円が
→14,000円に!
(リピート価格2,000円引き)
●レンジフード16,000円が
→14,000円に!
(リピート価格2,000円引き)
トータル通常価格合計44,000円のところ
➡ お支払い合計金額 38,000円(税込み)になります!
※以前にモップスにご依頼いただいたお客様でチケットがお手元に無い場合、お客様リストには記載がありますので、安心してリピ割でご依頼ください。
さらに、口コミ投稿くださった方には5つの特典をプレゼント中!
ワンタップで問合わせする→0120-438-890
対応エリア
上尾市
伊奈町
蓮田市
さいたま市(北区/西区/桜区/大宮区/中央区/浦和区/南区/見沼区/緑区/岩槻区)
ふじみ野市
富士見市
志木市
川越市
川口市
蕨市
戸田市
注意事項
- クリーニングをするにあたり電気、水道をお借りいたします。
- 10年以上前の製品は、補償対象外とさせていただきます。
- 異音がしている換気扇は、事前確認させていただきます。
- 汚れ具合によってはクリーニングで完全除去できない場合もございます。
- 3M以上高所に取り付けている換気扇は対象外とさせていただきます。
- 油汚れと塗装面の状態によっては、汚れを残さず落とそうとすると塗装も一緒にはがれてしまう可能性がございます。その際はお客様とご相談のうえ作業させていただきます。
- レンジフードの中には、ファンが外れないものもございます。外れないものはつけたまま清掃させていただきます。その際は一度ご相談させていただきます。特に外国製などの特殊なレンジフードは、事前に説明書あるいはメーカーにて確認をお願いいたします。当日にお伺いして、外れない場合でも料金は変わりません。十分ご注意ください。
- レンジフードクリーニングの後にまれに異音がするケースがございます。これは、長年の使用で付着した油により、回転バランスを崩したファンを清掃し、油汚れを取り除くと、バランスを崩していたファンが正常に戻ろうとして、異音が発生する場合があります。この場合しばらくファンを回しておくと自然に直ります。
- あくまでも家庭用レンジフードが対象になります。業務用レンジフードは承ることができません。
- レンジフードの横幅が1m以上の場合は別途ご相談ください。横幅が1m未満のものを対象としております。
- 油汚れを取り除くさいに洗剤を使用することで設備の種類によって質感が変わることもあります。
- レンジフード内部のクリーニングは研磨することにより素材に細かな傷がつく場合がございます。
お申込み・お見積りについて
お見積もりは基本的に無料です。
お支払いについて
本サイト上では、お支払いはできません。
基本的に作業終了後、仕上がり確認をして頂き、問題ないようであれば現金でのご精算になります。
※クレジットカードでのご精算は対応しておりません。
キャンセルについて
ご予約頂く場合は、確実な日程でお願い致します。
当日キャンセルの場合には、キャンセル料として作業代金の100%をいただきます。
キャンセルの場合には事前に電話でのご相談を早めにお願いいたします。
またキャンセル料をいただく場合にはこちらからお客様に振込先のご連絡をいたしますのであらかじめご了承ください。
その他
サービス内容や料金は予告無く変更する場合がございます。
基本的に、税金など全て込みの金額で提示しておりますので、当日作業内容が増えたりしない限り、追加料金は一切発生しません。