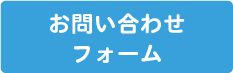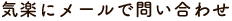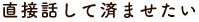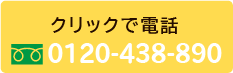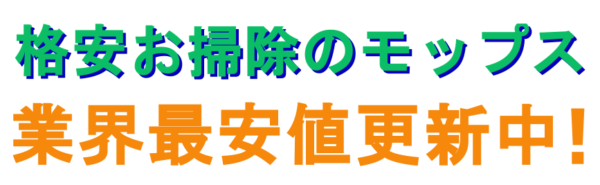これってカビが原因?”どこにでもいるカビが起こす”8つの気になる不調とその病名

梅雨が本格化した頃に日テレニュース24でも取り上げられた、「カビ由来の病気」。
みなさんは、カビ胞子が原因で引き起こされる症状についてご存知でしょうか?
単なる風邪だと思っていた症状が、実はカビによるものであるケースは少なくありません。
深刻な病気にかかる前に予防策を実践したいものですよね?
そこでこの記事では、”カビが起こす”8つの気になる不調とその病名について解説します。
カビ由来の病気を予防する方法についてもお伝えしますので、最後までお見逃しなく!
気になる不調とその病名
カビを吸い込んだ場合、主に咳・痰・息切れ・発熱・嘔吐・頭痛・皮膚炎・眼の充血痛みといった8つの不調が生じます。
一見すると風邪にも似た症状ですが、実は重大な病気を知らせる症状ということも…。
以前、お片付けとハウスクリーニングのご依頼を受けて伺ったお宅で見た光景は、締め切ったお部屋の中の天井まで届きそうなホコリだらけの山積みの物と雨戸の戸袋の中に作られたフンだらけの複数の鳥の巣。
咳が続くと受診した内科医から、レントゲンに白い影がある、今すぐ家から引っ越すことを考えなさいと言われたそうで、そう言われても…と、家中の片付けとお掃除を決心されたそうです。
人生の長い時間を過ごす自宅の空気がカビの胞子漂う空気だなんて、想像したくないですよね?
あなたは大丈夫でしょうか?
自分の身に同じような症状が無いか?あなたのお部屋にカビが生えている場所は無いか?思い出しながら、カビが引き起こす可能性のある病名についても詳しく見ていきましょう。

咳・痰・微熱・息切れなどの夏型過敏性肺炎
湿度が高まりやすい6月から10月にかけては「夏型過敏性肺炎」の感染者が増えます。
こちらは、湿気が溜まりやすい木造住宅の中、除湿・換気が行われていない場所、水回りなどを好んで生息するトリコスポロン・アサヒというカビ由来の病気です。
主に咳・痰・微熱・息切れなどの症状があらわれ、重症化すれば呼吸困難や皮膚・唇の変色を伴うこともあります。
咳・痰・微熱・血痰の肺アスペルギルス症
同じくカビ由来で肺の病気としては、「肺アスペルギルス症」が挙げられます。
こちらも咳・痰・微熱を伴い、重症化すれば血痰が出ることも…。
その原因となるのは、アスペルギルス・フミガタスというホコリに潜むカビです。
ホコリは掃除の行き届かないエアコンや部屋の隅などに溜まりやすく、私たちは無意識のうちにそれを吸い込んでしまうことがあります。
吸い込んだホコリの中にフミガタスが含まれていれば、たちまち体内でアレルギー反応を起こし、肺アスペルギルス症に感染することがあるわけです。

皮膚炎(発疹・かゆみ)のアトピー性皮膚炎
皮膚に特有の発疹ができ、汗をかくとかゆみを伴うことで知られる「アトピー性皮膚炎」が悪化する原因もカビ由来のたんぱく質にあります。
これを突き止めた広島大学の秀道広教授によれば、汗をかいたときに「MGL-1304」というカビ由来のたんぱく質が皮膚に馴染むと炎症が強まってしまうのだとか。
MGL-1304を生み出す「マラセチアグロボーザ」は人間の体内にある常在菌であり、皮脂分泌の多い部位や高温多湿な環境を好むカビの1種です。
皮膚炎(かゆみ・かぶれ・皮むけ)のいんきんたむし/水虫
白癬菌というカビ由来の病気としては、「いんきんたむし」と「水虫」が挙げられます。
汗や皮脂の残るアルカリ性の皮膚・湿気の多い環境を好む白癬菌は感染力が強く、感染者から剥がれ落ちた皮膚の中にも含まれているのです。
いんきんたむしや水虫患者の履いたスリッパや素足で歩いた床の上にも白癬菌が付着しているため、同じ場所を素足で踏めば高確率で感染してしまいます。
これらの病気はアレルギー性皮膚炎の1種であり、かゆみ・かぶれ・皮むけのほかに患部から悪臭が漂う場合もあります。
発熱・嘔吐・頭痛の真菌性髄膜炎
発熱・嘔吐・頭痛の症状を伴う「真菌性髄膜炎」は、鳩のフンに含まれる「クリプトコッカス・ネオフォルマンス」という名のカビが病原体となって発症する病気です。
道路に落ちた鳩のフンに含まれる微細なカビは風が吹くたびに地上へ舞い上がり、空気中に交ざります。
免疫力の低下した人間がその空気を吸い込みことにより、鼻腔や口内からカビが侵入して病巣を作るわけです。
クリプトコッカスによる代表的な病名は真菌性髄膜炎ですが、人によっては脳や中枢神経にまで病巣が広がることがあります。
眼の充血・痛みの角膜真菌症
眼の充血や痛みが続く「角膜真菌症」は、病原性の「真菌」というカビ由来の病気です。
患部となる角膜をコンタクトレンズや爪などで傷つけてしまった場合に、そこが真菌の侵入経路となって角膜真菌症を発症することがあります。
また、真菌は植物の葉・枝や庭の土などにも生息しています。
植物に触れた後で手洗いをせずに眼に触れた場合や、木の枝で角膜を突いてしまった場合にも同病に感染しやすくなるのです。
すでに眼の病気に感染している方・過去に感染したことのある方も角膜真菌症を発症しやすいといわれており、完治までは相当の期間を要します。
皮膚炎(デリケートゾーンのかゆみ)のカンジダ症
デリケートゾーンのかゆみを伴う「カンジダ症」はカンジダ菌というカビ由来の病気です。
感染者は女性のみで、抗生物質を投与された後や免疫力が低下した状態で発症する傾向があります。
カンジダ菌は女性の膣内に生息する常在菌であり、ホルモンバランスの低下によって炎症が慢性化することもあるのです。
江本智子ウィメンズクリニックの医師・江本智子さんによれば、皮膚や患部が蒸れやすい下着を着用しているとすぐに再発する可能性があるようです。

【シーン別】あなたの生活に潜む健康を脅かすカビの影
屋内・屋外を問わず浮遊するカビは様々な不調や病気のもと。
その不調は風邪の症状とよく似ており、素人目には判別が難しいといわれています。
日テレニュース24によれば、私たちが1日に吸い込むカビ胞子は1万個だとか。
わずか0.01ミリから0.1ミリほどのカビ胞子を肉眼でとらえることは難しく、気づかないうちに吸い込んで病気になってしまうわけです。
ここでは、そんなカビ胞子が潜む場所をシーン別にお伝えします。
え~!?こんなところにも?屋内でカビが発生する4つの場所
水回り
キッチン、洗面台、浴室、トイレ、排水口などの水回りはカビの代表的な生息地。
カビは基本的に高温多湿な場所を好むため、洗濯機の中なども繁殖しやすいスポットです。
シャワーのホースや水道の蛇口まわりには水が溜まりやすく、必然的にカビの生えやすい湿潤な場所になっていきます。
湿気がこもる場所・モノ
押入れやクローゼットの中、タンス、収納ボックスの中などの湿気がこもる場所にもカビは発生します。
同じく湿気がこもりやすいカーテン、敷布団、クッションといった物からカビが繁殖する場合もあるのです。
でも、なんといっても一番怖い湿気のこもる場所はエアコンです。クーラーモードにした際、エアコンのフィンと呼ばれる熱交換器の部分には大量の湿気が発生し、エアコン内に吸い込まれる空気の中のホコリと合体し、カビの温床となります。
ですから、気が付かないうちにあなたも、大量のカビが生えたエアコンから出てくる風を「涼しくてきもちいい♪」と有難がっているかもしれません・・・。
動かさない家具の裏側
テレビ、洗濯機、冷蔵庫、食器棚、エアコンなどの重い家具はめったに動かしませんよね。
実はその裏側にもカビが生息しているのです。
重い家具の表面だけを乾拭きして掃除を終えている場合は、特に多くのカビを見落としているでしょう。
電化製品
驚くべきことに、カビは静電気の発生する場所にも生息しています。
パソコン、カメラ、コピー機、固定電話、スマホなどの電化製品にも付着しているのです。
仕事や私生活など日常的に使用する電化製品はこまめに掃除をし、高温多湿な環境でカビの繁殖を増進させないようにしなければいけません。
さて、次は屋外ですね。
家の中だけじゃない!屋外でも気を付けるべきカビが発生する場所5つ
庭の土/庭の植物
カビの発生源は屋内だけだと考える方は意外に多いです。
しかし実は、庭の土や植物にも、「フザリウム・ベルチシリオイデス」という感染性の高いカビが生息しています。
このカビが眼に侵入した場合は、先にお伝えした角膜真菌症を引き起こすことも…。
したがって、屋外に出れば安全というわけではないことを理解しておきましょう。
地面/床下
道路(地面)や飲食店の床などにもカビは発生します。
鳩のフンは地面に落ちてカビを空気中に散布させますし、飲食店の床はモップがけがなされて湿ることでカビが発生しやすい環境となるわけです。
排水溝/マンホール
ヘドロのような粘り気のある黒カビが発生する場所といえば、屋外の排水溝やマンホール。
いずれも常に水が流れて湿潤な環境となっているため、カビが繁殖しやすいのです。
降水量の多い梅雨時期に至っては、排水溝やマンホールに溜まった下水が溢れ返ることも。
この下水の中に含まれるカビが皮膚に付着して病気に感染するケースもあるのです。
公園の砂場
子どもたちを遊ばせる公園の砂場にもカビは発生します。
すでにこの事実を知る保護者は事前に「砂場用抗菌剤」を準備し、それを撒いた上で子どもを遊ばせているのです。
木材
住宅メーカーが使用する木材に黒カビ・青カビなどが発生することもあります。
知っての通り、木材は金属に比べて湿気を吸収しやすいですよね。
湿気は降水量にかかわらず、蒸し暑い環境下で待機中に蓄積されてしまいます。
雨が降らない日でもカビが木材に繁殖することを防ぐのは難しいわけです。
すぐにできる!カビ由来の病気を予防する3つの方法
どこにでも生息することができるカビは、私たちの日常生活の中にも潜んでいます。
そこで最後に、カビ由来の病気を予防する3つの方法を紹介します!
カビについて知識のない初心者でもすぐに実践できるポイントです。
病気の感染源と隣り合わせに暮らしていることを意識し、予防策を活用してくださいね。
◆カビを生やさない
既存のカビを除去する前に、「カビを生やさない」ことを前提にしましょう。
今暮らしている環境の改善なしにカビを徹底除去することはできません。
水回りのカビは50度以上の熱湯で撃退する
カビを生やさないようにするためには、「熱湯消毒」が1番です。
高温多湿を好むカビも、45度以上の環境下では死滅してしまいます。
1.水回りのカビは「50度以上の熱湯」で撃退する
2.カビを新たに繁殖させないよう、水分はスクイージで拭き取る
3.掃除した場所から湿気が完全になくなるまで換気を行う
上記の順番を守ってカビを予防してみてください。
もしも換気扇が不調な場合は、丸めた新聞紙を敷き詰めて扇風機を回すのがおすすめです。
家具と壁の間にスキマを作っておく
重い家具はめったに動かさない分、その設置方法を工夫する必要があります。
家具と壁の間に数センチだけでもスキマを作っておきましょう。
几帳面な方ほど家具をぴったりと壁につけて設置するのですが、これでは湿気がこもるばかりでカビの繁殖を促してしまいます。
自力で既に置かれた家具の配置をずらせない場合は、男性の手や引越し業者などを上手く活用しましょう。
◆カビをガードする
ある程度までカビを生やさない努力をしたら、「カビをガード」しましょう。
ここでいうガードとは、カビ予防アイテムを駆使するという意味です。
タンク型、シート型除湿剤や窓の結露やお風呂の水滴をペットボトルに溜めることができるスクイージ、押し入れ湿気防止用にすのこ、カビ防止シール等100円ショップやネット通販サイトには予防・除去アイテムが多数出回っています。
銀イオンやバイオのような効果的な成分を使いながらも、肌・手・口に含んでも害のないカビ防止製品が続々登場していますよ!
◆カビを除去する
最後に考えるべきことは、「すでにできてしまったカビを除去する」ことです。
これをそのまま放置しておくわけにはいきませんので、以下を参考にお掃除しましょう。
|
泡タイプ、ジェルタイプのカビ取り剤、アルコール除菌スプレー等100均でも手に入れることが出来ますので、ぜひ、試してみてください。
自力で取れないカビはプロに任せて徹底除去!
屋内外を問わず、時間が経って広範囲に広がってしまったカビは、頑固で取り除きにくいのが特徴…。
上記の方法で手に負えないカビの掃除はプロに任せましょう。
ただし、稀にプロでも除去できないカビがあります。
水回りを例に挙げるなら、「浴室のパッキンに付着した根の深い黒カビ」ですね。
ゴムの奥深くに広がってしまったカビはカビ取り剤が届かず、取り除くのは不可能なのです。
プロの力をもってしても取り除けなさそうなひどいカビは、“物理的にカビの生えた部分を取り除く”ことも選択肢の1つとして考えておきましょう。
自分でやるのは自信ないとおっしゃる方は、内装業者さんに頼めば確実ですが、
交換用パッキン、目地用白ペン、こんなプロが使うような物まで100均にはあるので、小さなところの修理なら挑戦してみるのもありかなと思います^^
業界最安価格で定期的にお部屋を清潔に保ちたい方は、
忙しい中コロナ対策をしたいけど、なるべく安く!というかたは、こちらから、お気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】業界初!モップスの「永久割引制度(リピ割)」とは?
これは、モップスで2回目以降のサービスご利用時に使える制度なのですが、
例えば、あなたが、初めてモップスのサービスをご利用になったとき、作業終了後、モップスから「リピ割チケット」をプレゼントいたします。
で、このチケット1枚で「10,000円以上の単品メニュー」がすべて2,000円引きになるうえに、チケット一枚で同時に複数のメニューを申し込むことも可能になる制度となります。
「今だけ!」永久割引権利プレゼント
さらに、この制度は、サービスを利用するたびに「永久に」適用されます。
つまり、今なら、どのようなコースでも、一度でもモップスのサービスを申し込んでくれたお客様にはチケットをお渡ししますので、2回目以降、そのチケットを出していただければ、その都度、各メニュー(10,000円以上の単品)について2,000円引きでサービスを受けられるということです。
言い換えると、一度でもモップスのサービスをご利用になれば、モップスとあなたが存在する限り、半永久的に使える「2000円引きパスポート」を手に入れることができる、ということ。
永久割引権利が得られるのは、本当に「今だけ」
この制度は大評判なので、なるべく続けたいと思っているのですが、定期的にリピートしてくださるお客様が一定数以上になった場合、スタッフの人数によっていやでも制限が生じる為、仕事の質を保つためには必ず一旦停止しなければなりません。
ですから、煽りでも、演出でもなく、本当に、この制度が停止する前に、権利をゲットしていただけたお客様だけが、めちゃくちゃお得になる状態なのです。
ちなみに、お掃除機能なしのエアコンクリーニングを、初回8,000円で利用するだけでも、この永久権利がもらえますので、「お試し」でトライするコストも業界最安と言えるでしょう。
モップスのコンセプトは「お客様を徹底的にえこひいきする!」ですので、リピーターのお客様には、他社圧倒の超お得な制度で歓迎いたします!
是非ご利用ください。
リピ割チケット(永遠に2000円引き)が適用できるコース一覧
- お掃除機能付きエアコンクリーニング
- 通常エアコンクリーニング
- トイレクリーニング
- 浴室クリーニング
- キッチンクリーニング
- レンジフードクリーニング
モップス2回目(チケットご提示)ご利用イメージ
例えば、モップス2回目でチケットをお持ちの方が通常エアコン1台とキッチン、レンジフードのクリーニングをお依頼くださった場合
●通常エアコン12,000円が
→10,000円に!
(リピート価格2,000円引き)
●キッチン16000円が
→14,000円に!
(リピート価格2,000円引き)
●レンジフード16,000円が
→14,000円に!
(リピート価格2,000円引き)
トータル通常価格合計44,000円のところ
➡ お支払い合計金額 38,000円(税込み)になります!
※以前にモップスにご依頼いただいたお客様でチケットがお手元に無い場合、お客様リストには記載がありますので、安心してリピ割でご依頼ください。
さらに、口コミ投稿くださった方には5つの特典をプレゼント中!
ワンタップで問合わせする→0120-438-890
対応エリア
上尾市
伊奈町
蓮田市
さいたま市(北区/西区/桜区/大宮区/中央区/浦和区/南区/見沼区/緑区/岩槻区)
ふじみ野市
富士見市
志木市
川越市
川口市
蕨市
戸田市
注意事項
- クリーニングをするにあたり電気、水道をお借りいたします。
- 10年以上前の製品は、補償対象外とさせていただきます。
- 異音がしている換気扇は、事前確認させていただきます。
- 汚れ具合によってはクリーニングで完全除去できない場合もございます。
- 3M以上高所に取り付けている換気扇は対象外とさせていただきます。
- 油汚れと塗装面の状態によっては、汚れを残さず落とそうとすると塗装も一緒にはがれてしまう可能性がございます。その際はお客様とご相談のうえ作業させていただきます。
- レンジフードの中には、ファンが外れないものもございます。外れないものはつけたまま清掃させていただきます。その際は一度ご相談させていただきます。特に外国製などの特殊なレンジフードは、事前に説明書あるいはメーカーにて確認をお願いいたします。当日にお伺いして、外れない場合でも料金は変わりません。十分ご注意ください。
- レンジフードクリーニングの後にまれに異音がするケースがございます。これは、長年の使用で付着した油により、回転バランスを崩したファンを清掃し、油汚れを取り除くと、バランスを崩していたファンが正常に戻ろうとして、異音が発生する場合があります。この場合しばらくファンを回しておくと自然に直ります。
- あくまでも家庭用レンジフードが対象になります。業務用レンジフードは承ることができません。
- レンジフードの横幅が1m以上の場合は別途ご相談ください。横幅が1m未満のものを対象としております。
- 油汚れを取り除くさいに洗剤を使用することで設備の種類によって質感が変わることもあります。
- レンジフード内部のクリーニングは研磨することにより素材に細かな傷がつく場合がございます。
お申込み・お見積りについて
お見積もりは基本的に無料です。
お支払いについて
本サイト上では、お支払いはできません。
基本的に作業終了後、仕上がり確認をして頂き、問題ないようであれば現金でのご精算になります。
※クレジットカードでのご精算は対応しておりません。
キャンセルについて
ご予約頂く場合は、確実な日程でお願い致します。
当日キャンセルの場合には、キャンセル料として作業代金の100%をいただきます。
キャンセルの場合には事前に電話でのご相談を早めにお願いいたします。
またキャンセル料をいただく場合にはこちらからお客様に振込先のご連絡をいたしますのであらかじめご了承ください。
その他
サービス内容や料金は予告無く変更する場合がございます。
基本的に、税金など全て込みの金額で提示しておりますので、当日作業内容が増えたりしない限り、追加料金は一切発生しません。
お問い合わせ